3年生の選択授業、ファッション造形基礎では、1学期に和服(浴衣)を製作しました。初めての和裁で、ミシン縫いや三つ折りぐけなどの手縫いに苦労しましたが、意欲的に取り組み完成しました。
7月10日、着付け講師の門屋朝美先生に来ていただいて浴衣の着付け実習を行いました。
浴衣の羽織方や、防犯のためにタンクトップなどの下着をきちんと身に着けることに始まって、丁寧に浴衣の着方や帯結び(ちょうちょ結び)を教えていただきました。
<生徒の感想>
「着付けをしたのは初めてだったので、難しかったけれどとても良い経験になりました。私は着物が好きなので、教えていただいたことを何度も練習して、人にも教えてあげたいです。」
「着付けは難しくて疲れましたが、楽しかったです。自分の作った浴衣を着れてよかったです。」
「いつもお母さんと一緒に着ていたので、一人で着る大変さを知りました。帯1本でリボンまで作れて感動しました。」
100均で購入して作る素敵な根付けの帯飾りや、おしゃれな帯締めも見せていただきました。
みんな浴衣がよく似合っていました。たまには着物でお出かけもいいですね!
2学期は洋服、3学期は手芸作品を作る予定です。製作が中心ですが、製作するための基礎的な知識も学習します。




7月18日研究の第一人者である古川勝三さんによる講演会が砥部分校で行われました。一般公開ということもあり、町役場の方を始め地域の方もたくさん参加されました。
会場には生徒作品や卒業生の作品を展示していたので地域の方が足を止めてご覧になる姿も見えました。
ご来場の方には、生徒作品のカードのプレゼントもありました!
講演後一般の方に感想をお伺いすると
「台湾と愛媛の人のつながりで知っているのは野球の近藤兵太郞さんだけでしたが、他にもいろんな貢献をしてきたことが分かりました。」
「昨年12月の議会で鶯歌区と砥部町の友好交流締結を提案しました。100年前に砥部の陶工が鶯歌の窯業発展のために陶芸を伝えたことは事実です。今日のお話でも古いつながりを感じました。」
「愛媛の人の貢献があって今の台湾があること。台湾の方に日本の精神が息づいていることを感じました。」
と振り返られました。
今回は講演会の様子を生徒や参加された方、講師の先生のインタビューを交えて
創部したてほやほやの広報同好会が動画でレポートします!

7月21日(金)、入道雲が取り巻く晴天の下、とべぶんでは多くの中学生のみなさんが「一日体験入学」に参加されました。
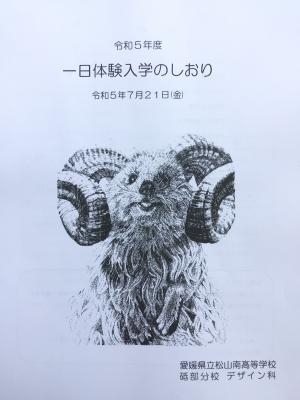 今年の参加者は、県内外から92名。高知県、城辺、伊方や三島からもお越しいただきました。
今年の参加者は、県内外から92名。高知県、城辺、伊方や三島からもお越しいただきました。
しおり表紙絵 3年 井上優月(久米中出身)




クロッキー実演を見学しながら、体育館にずらりと並んだ在校生、OBの作品群にも足を止めるみなさん。「...すごいねー...」という声が聞かれました。
開講行事の後は、6つのワークショップに分かれて体験実習です。
CG I:[パソコンを使ったデザイングッズ制作]



先輩A「ち、ちゅう、中学生の皆さんうますぎです〜」
CG II:[パソコンを使ったアニメーション制作]


「初めてとは思えないくらい動かすのうまい」と先輩B談。
わからないことは質問し、サクサク作業が進みます。


素描:[自然物・人工物などを鉛筆を用いて描く]



インパクト強めの会場レイアウトに気分もUP
水彩表現:[水彩絵具を使った様々な表現技法の体験]
先輩の手元が前に映し出されて参考になります。



陶芸:[ロクロを使った成形技法の体験]



 先輩と楽しく活動。いい感じ♪
先輩と楽しく活動。いい感じ♪
今年は、ワークショップと並行して、保護者の皆様、中学校の先生方を対象に座談会ルームを設け、とべぶんへの質問や入試、進路などさまざまな不安・疑問点の解消を図りました。座談会にはとべぶんOB・その保護者の方々が応援に来てくださり、経験値から言えるリアルなアドバイスを提供してくださっていました。





県内のみならず全国で活躍する先輩方の作品も展示されました。
 中学生の皆さん、今日という日が心に残る良い日でありますように、お祈り申し上げます。
中学生の皆さん、今日という日が心に残る良い日でありますように、お祈り申し上げます。
準備や当日の応援に携わってくださった、在校生のみなさん、OBの方やその保護者の方々、そして、先生方、本当にほんとうに、お疲れ様でした!
「8月18日(金)のデッサン講習会も、お待ちしてます‼︎」
本校卒業生の山本修司さん(S52卒)が愛媛ゆかりの気鋭の作家を紹介する企画展UP And Coming展Ⅲに出品されています。
山本さんの作品や制作への思いについて、愛媛新聞(7/4付)では丁寧に取り上げられています。
企画展は8月6日まで、ミウラートヴィレッジで開催中です。是非お運び下さい。
「愛媛ゆかり 気鋭の芸術家」2023年7月4日付愛媛新聞
(掲載許可番号:d20230705-01)

先日防災訓練が行われました。
今回の防災訓練は、地震の影響で火災が発生する想定で行われました。

実際の地震を想定し、机の下で頭を守ることや、避難経路確保のために教室の扉を開けるなどを行った後に、避難場所にある体育館に迅速に移動しました。

生徒に感想を聞くと「自助、共助を大切にしていざという時に率先して行動することの大切さを学ぶことができました」と言っていました。